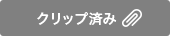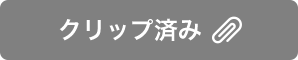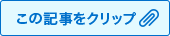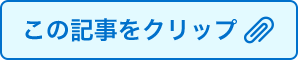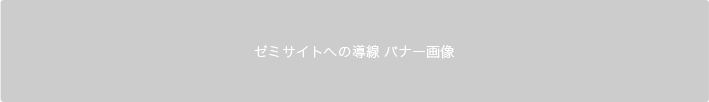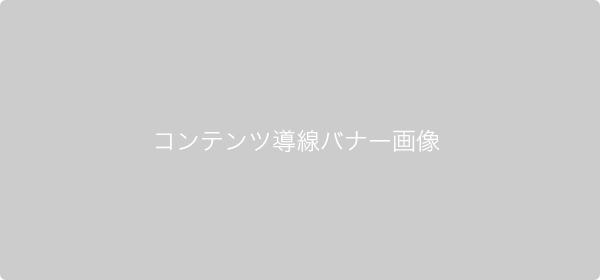プログラミング教育で伸びる力!論理的思考力が未来を切り開く

「プログラミングって、将来エンジニアを目指す子のためのもの?」そんなふうに思っている保護者のかたもいるかもしれません。現在プログラミング教育は、職業スキルを身に付けること以上に「論理的思考力」を育て、その思考を見える化するという役割に注目が集まっています。なぜならAI時代においては、ただ正解を出す力ではなく、正解に至るまでの思考プロセス(思考の過程)を大切にしながら、自分の頭で考え、課題を解決し、そこから新しい価値(イノベーション)を生み出す力が求められているからです。
今回は、プログラミングに長く精通し、イノベーション人材の育成にも取り組まれている崇城大学の星合隆成先生に、プログラミング教育と論理的思考力についてお話を伺いました。
この記事のポイント
今、なぜプログラミング教育なのか?

プログラミングとは、「プログラミング言語」という特別な言葉を使用し、コンピューターに特定の作業を実行させるための指示書を作成することです。プログラミングはさまざまなものに活用されており、家電、スマートフォンアプリ、ゲーム、Webサイト、ロボットなど、私たちの身の回りにあふれています。
そのため、プログラミングを学ぶことで、プログラマーやシステムエンジニアなどのプログラミングを使う職業に就ける可能性が広がります。しかし、現在ではAIがコードを自動生成する時代に突入しており、「プログラムを書く」という技術的な目的だけでは、学ぶ意味が薄れつつあるのです。
「では、なぜプログラミング教育が必要なの?」と思われるかもしれません。その答えになるのが、プログラミングを通じて学ぶことができる「論理的思考(ロジカルシンキング)」にあります。プログラミングは、論理的思考力を養うことと、その思考プロセスを見える化することに最適なツールなのです。
プログラミングは論理的思考力を養うのに最適のツール!
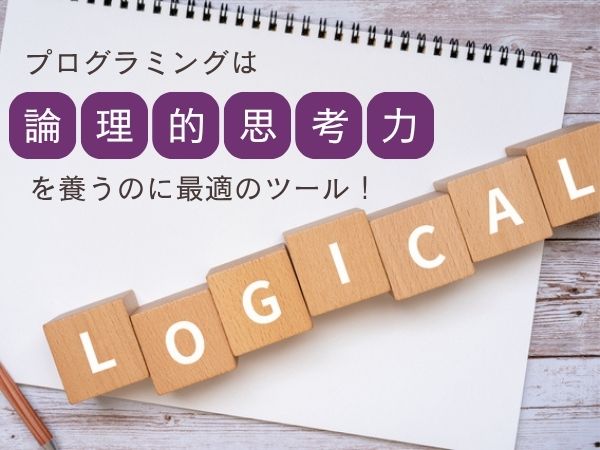
そもそも、論理的思考力はなぜ必要なの?
論理的思考力とは、「筋道を立てて考える力」を指します。問題の本質を理解し、原因の分析に基づいた解決案を考え、その結果を評価するという課題解決に不可欠な力です。
そして、プログラミングを通じて養われる論理的思考力は、新たな発想や視点で「新しい価値を生み出す力」や「社会の変革を担う力」ともつながっており、今後ますます必要とされる能力といえます。
社会における仕事には大きく2つ、「課題解決」と「価値創造」があります。「課題解決」と「価値創造」の関係は、「縦ぐし」と「横ぐし」の関係です。「課題解決」が「縦ぐし」ならば、「価値創造」は「横ぐし」です。
目的やゴールがはっきりしている「課題解決」を通じて得られる多くの経験や知見に対し、横ぐしを刺すことによって、「価値創造」は生まれます。したがって、正解に至るまでの思考プロセス(思考の過程)を大切にしながら、課題を解決する時に必要な論理的思考力は、新たな価値を生み出す「価値創造」に対しても必要になる能力なのです。
論理的思考力を養うことで、複数の視点で物事をとらえられるようになり、将来的には新しい価値を生み出せる「イノベーション人材」が育つのです。
論理的思考力を養うために、プログラミングがおすすめの理由は?
論理的思考力を養うために、なぜプログラミングがおすすめなのでしょうか?
その理由は、プログラミングにおける「条件分岐(条件に応じて行うべき処理を切り分けること)」が、あらゆる可能性を論理的に整理し、対応策を考えるための最適な訓練になるからです。
たとえば、コンピューターに指示を出す時、「どういう条件の時に」「何を」「どの順番で」「どうやって」動かすかを、正確に伝える必要があります。これはまさに、論理的に考える力が問われる場面です。プログラミングでは論理的思考を見える化できるのです。
プログラミングを論理的思考力を養うためのツールとして用いるさらなるメリットとしては、誰かと比べられることなく、自分のペースで進めることができ、なおかつ失敗してもすぐに何度でもやり直せるという点が挙げられます。プログラミング教育では、失敗も学びにおける大事なステップです。
「思ったように動かなくても、どこがまちがっていたのかを考えて修正する」
そんな試行錯誤のプロセスが、子どもたちの「考える力」の育成につながります。
安心して失敗できる環境は子どもたちにとって、非常によい学習環境でもあります。
家庭でできる! 論理的思考力を育てるために大切なこと

もちろん、論理的思考力を養うために、プログラミング以外でもできることはたくさんあります。たとえば、保護者のかたとお子さまとの何気ない会話もその一つです。
子どもの疑問や発見の芽を大事にする
「海の水がしょっぱいのはどうして?」
「飛行機はなぜ飛べるの?」など、
多くの保護者のかたが、お子さまの質問に対して「どう説明したらいいの……?」と困った経験があるのではないでしょうか?
お子さまの疑問や考え、発見こそ、考える力の種になります。もしその場で質問に答えられなかったとしても、「なんでそう思ったの?」「不思議だね! 面白いね!」「あとで一緒に調べてみようか」と、子どもの考えや発見に耳を傾けるだけで、子どもの考えようとする意欲は膨らんでいきます。
子どもの「なんでなの?」を大事にして、その芽をつぶさないことが大切です。
答えをすぐに教えず、問いかける
「これどうしたらいいの?」と聞かれた時、すぐに「こうしなさい」と答えを教えるのではなく、「どうしたいの?」「どうすればうまくいくと思う?」と問いかける姿勢も大切です。
できれば「失敗してもいいんだよ」と伝えてあげてください。失敗してもいい環境は、子どもたちに安心感を与え、「もう一度チャレンジしてみよう」と思える原動力になります。
「うまくいかない経験も成長のチャンスなんだ」と理解し、うまくいかない時にも「挑戦したことが偉い」「考えたこと自体がすごいよ」とプロセスを認めてあげると、子どもは前向きに学び続けることができます。
まとめ & 実践 TIPS

プログラミング教育は、将来のプログラミング関連の職業に直結するだけでなく、AI時代に必要な論理的思考力、ひいては、課題解決力や価値創造力を育む最適なツールです。失敗を恐れずに、試行錯誤する経験を通じて、子どもたちは「自分で考える力」を身に付けることができます。ご家庭でも子どもの疑問を大切にし、これからの時代に必要な「生きる力」、さらにはイノベーションを起こせる力を、一緒に育んでいきましょう。
編集協力/海田幹子